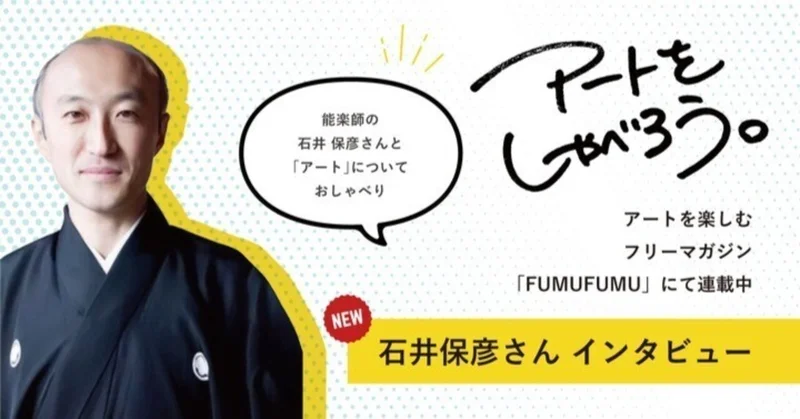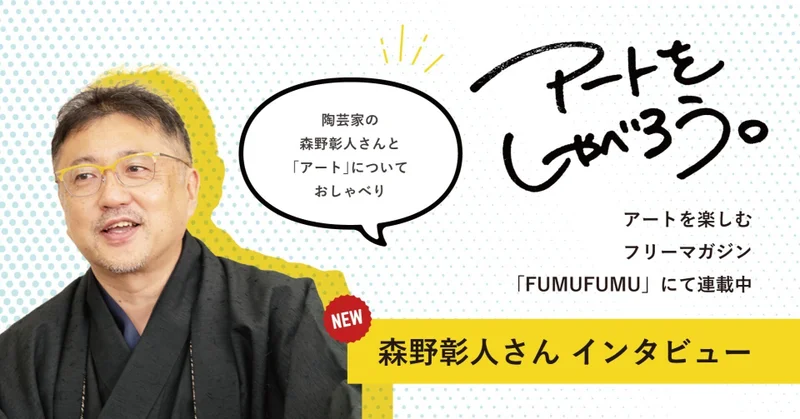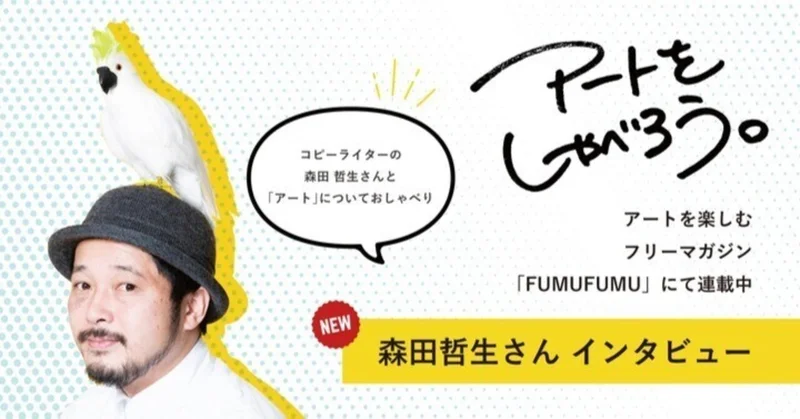能楽師の石井保彦さんと「アート」についておしゃべり。日本の伝統芸能として、どこかハードルが高く高尚なイメージのある「能」ですが、実際に体験してみれば、そこはとても自由で美しい世界。実はフリーランス集団(?)だという能楽師の働き方事情から、今まで知らなかった豆知識まで。絵画とは遠いようで近い、能の世界にせまります。

石井保彦(いしいやすひこ)
昭和39年生まれの能楽師。京都能楽囃子方同盟会会員。石井流大鼓方、石井流十三世宗家。谷口正喜、石井仁兵衛に師事。重要無形文化財総合指定保持者。
京都能楽囃子方同盟会公式サイト:https://noh-doumeikai.com/

「この美しい世界で生きていくのも悪くないな」と思った
━━日本の伝統芸能として知られている「能」ですが、一般的にはあまり馴染みのない人も多いですよね。ハードルの高さを感じやすいという点では、絵画と少し共通点もあるのかなと思っています。
石井保彦(以下、石井):そうですね。これを読んでくださっている方も、能の舞台を観たことがない方が多いのではと思います。でもそれが普通なんですよね。僕自身もこの世界に入る前は、能のことを「よく分からない」「辛気臭い」なんて思っていましたから(笑)。
━━え、そうなんですか!?
石井:僕の家は、能楽師の中でも代々「鼓」をやっている家系でしたが、元々は能楽師になる予定はなく、世界で活躍する外交官になりたいと思っていました。稽古自体はずっとやっていたものの、能楽師になるのは嫌で嫌でしゃあなくて(笑)。ただ、高校3年生の頃、父が病気で倒れたことをきっかけに、僕の中に「能楽師になる」という選択肢が生まれたんですよね。その後半年で、父は舞台復帰できたのですが、大学生になり、かばん持ちで舞台について行ったりするうちに、能はとても美しい世界だということを知ったんです。その時「この美しい世界で生きていくのも悪くないな」って思ったんですよね。

━━実際に体験していく中でイメージが変わったんですね。
石井:そうですね。例えば、能装束(能で使われる衣装)は、美術館とかでも観ることができるのですが、実際に能楽堂の中で身につけている能装束は美しさが全く違っていて、生で観ることで、今まで気づかなかった豪華さや美しさに気づいたんです。能に関わらずスポーツや音楽でもそうだと思うんですけど、映像や写真で観るのと生で観るのはやっぱり全然違いますよね。これは絵画も同じなのではないでしょうか。目の前にある原画だからこその美しさやエネルギー(波動)がありますよね。そういった「生」の魅力を、皆さんにぜひ感じてみて欲しいと思っています。
能楽師はフリーランス集団?
━━そもそも能の仕組みが分からないという人も多いと思うのですが、能の舞台はどのようなメンバーで構成されているんでしょうか?
石井:能の役者には、歌(謡-うたい-)と舞をする主人公の「シテ方」、その相手となる「ワキ方」、狂言の演技を専門にする「狂言方」、僕のように楽器を専門とする「囃子方」という役割があります。僕は囃子方の中でも大鼓(おおつづみ)という楽器が専門です。これらの役割はそれぞれが専門でやっているので、シテ方の人がワキ方や狂言方、囃子方をやることはありません。また同じく日本の伝統芸能である「歌舞伎」と一緒くたにされがちですが、全く別物なんですよ。
━━確かに似たイメージですよね。大きく異なる点はどこですか?
石井:まず、興行形態自体が全然違うんです。歌舞伎は、役者、大道具、演出など全てを、松竹という会社が運営しています(※一部例外もあり)。なので、売上を上げるためにTVに出るようなスターを輩出していくんですよね。皆さんも歌舞伎役者の名前を、何人かは思い浮かべることができるはずです。 それに比べて能は、自営業者の集まりなんですよ。江戸幕府や各藩がお抱えしていた時代は、お扶持(おふち-給料みたいなもの-)をもらっていたのですが、明治時代になると幕府や藩がなくなったので、能楽師はみんなそれぞれ自営業者になり、また廃業された方も多かったのです。

公演の様子
━━能楽師の方たちって、意外にも“フリーランス集団”だったんですね。
石井:そうそう。感覚としてフリーランスである自覚はないんですけど、実際にはそうですね(笑)。数名で舞台をやっているのでよくチームだと思われるんですけど、そういう訳でもないんです。その公演ごとにメンバーを集めて終わったら解散、次回の公演はまた違うメンバーでやるんですよ。
━━能楽師の方たちって、なんだか高尚なイメージがあるのですが、普段はどう過ごされているんですか?
石井:全然普通の人ですよ。普段はもちろん私服ですし。あ、普段から着物で過ごしている人も数人いますね。多分服持ってないだけだと思うんですけど……(笑)。
能って、遠い存在のようで、意外と皆さんの生活と近いものなんですよ。たとえば、株式相場で使われる「仕手株(してかぶ)」というのは能の「シテ方」、「脇役」という言葉は「ワキ方」に由来していると言われていたり、雛人形の「五人囃子(ごにんばやし)」なんかも、謡(うたいを謡う人)と笛と鼓が3つ(小鼓、大鼓、太鼓)で、能の演奏だったりします。知らず知らずのうちに、能がルーツになっているものと触れているんですよね。番組、檜舞台、打ち合わせ、なんかも能から来た日常語ですね。
能と絵画、楽しみ方の共通点
━━能を鑑賞してみたいとは思っているものの、なかなか踏み出せない人って、すごく多いような気がします。初めて行った人でも、理解できるものなのでしょうか?
石井:正直なところ、TVや映画を観る感覚で行くと、理解できないかもしれません。というのも、映画やTVは予備知識なく観れますが、能は「ストーリーの内容を事前に知っておくこと」が楽しむ秘訣なんです。たとえば「浦島太郎」のお話はみんなが結末を知っていますよね。結末やストーリーの展開を知りながら、それを舞台の中でどう描くのかというところが能の見どころ。もちろん予備知識なしに観にいくこともOKですが、予備知識があったほうが楽しめることは間違いないと思います。
━━絵画でも近い部分があるかもしれないです。何も知らずに観ることもできますが、知識があるとさらに楽しめるので。
石井:確かにそうですね。僕が美術館に行った時にも、それはよく感じます。同じ絵でも、知識を持っている人は食い入るように鑑賞されていたりしますよね。

石井さんの演奏する鼓
━━情報過多な現代だからこそ、そういった「能動的に楽しむもの」の価値も注目されてきているように思います。
石井:そうですね。踏み込むまでは時間がかかるかもしれませんが、行動した先にある楽しみが大きいんですよね。能でも絵画でも、理解度が進んでいくとどんどん深い世界へ入っていける。コアなファンが多いのも、それが理由なのかと思います。Casieさんで言えば、レンタルした期間や枚数に比例して、理解度や豊かさが高まっていくのではないでしょうか。最初は誰もが「分からない」という状態ですが、それでも体験してみることって大事。極論を言えば、能を観に来て、寝ていてもいいと思うんです。
━━え、寝ていてもいいんですか?
石井:はい、能って実はすごく自由な芸能なんですよ。能楽師は、能装束の色も面の選び方も自由。それと同じでお客様の鑑賞方法も自由で良いんです。能楽堂ってα波がすごく出ているんですよね。歌のリズムは七五調になっていて、日本人の心にスッと入ってくるテンポだったり、いい演奏を聴いていると豊かな気持ちになって、眠気に襲われるのは極々自然なこと。それに従うのは、心と体にとって非常に良いことですよね。演奏が下手だったら、眠るに眠れないので(笑)。
━━そう言われると、なんだか気が楽になりました。能楽堂でぼーっと過ごす時間もなんだか贅沢だし、そこから深い世界に入っていくのも良いかもしれないです。
石井:気になった方は、各地域に能楽堂があるので、ネットで検索してみてください。最近では公演前にストーリーの説明をしながら「ここのこういう動きはこんなことを表現しているんですよ」と解説をしてくれることも多いので、初めての方はそういった解説付きの公演を選んでみると良いかもしれません。どんな形でも良いので、ぜひぜひ気楽に観に来ていただけたらと思います。