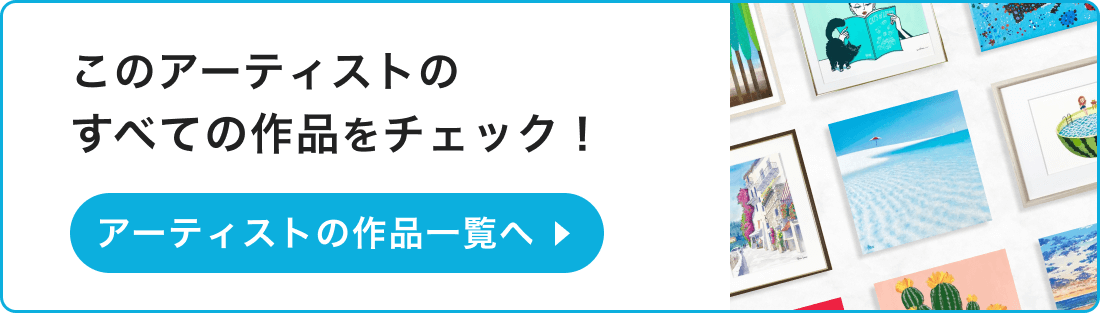アートは見た目だけでなく、アーティストによって込められた想いや制作の裏側に隠れたエピソードなど、様々な角度から見る楽しさがあります。そんな数多くの作品たちの一風変わった姿を紹介するのが、おしえて制作のヒミツ。
今回は「“冒険の感動”を描く、絶景アート」をテーマにR.takiさんの作品の魅力に迫ります!
R.taki
鹿児島県出身、京都府在住のアーティスト。登山や旅先で出会う自然や絶景の感動を如何に表現できるか、伝えられるかをテーマに作品を数多く制作する。写真の様に忠実に再現したものではない味わいのある作品が魅力。
《「断崖の吊り橋」大杉谷》
サイズ:H63.5cm × W48.6cm
「登山」や「旅行」が大好きなR.takiさん。夫婦仲良く様々な場所へと積極的に足を運ぶのが日課だそう。
《「断崖の吊り橋」大杉谷》は、三重県多気郡大台町にある大杉谷のトレッキング中に目の当たりにした「圧倒的な迫力」と「張り詰めた緊張感」を表現した作品となっています。
この作品には一体どんなヒミツが隠れているのでしょうか?
ヒミツ①「水から生まれる自然な色の交わり合い」
1つ目のヒミツは、R.takiさんが描くすべての作品に共通する“自然な色の重なり”に迫ります。
自ら足を運んだ場所を水彩画として描くR.takiさん。
そんな彼が描く水彩画には、全ての作品で用いられている共通の技法があるのだそう。
その技法とは、ウェットインウェット(Wet in Wet)。(※1)
R.takiさんは「水彩画の一番の良さは、ウェットインウェットの技法を使えることだと思うんです」と話します。
※1
ウェットインウェット(Wet in Wet)とは?
水や絵の具の濡れている状態を利用して、その中に絵の具を塗っていく技法。水や絵の具が乾く前に異なる糸の絵の具をのせることで、境界線のない柔らかな色合いを表現することができます。「にじみ」の表現として水彩画で用いられる表現技法の一つです。
《「断崖の吊り橋」大杉谷》では、美しい紅葉や聳え立つ岩肌の表現に用いているのだそう。
「筆の運びから生まれる意図した表現ではなく、描いている自分もどうなるかわからない、自然な色の交わりや広がりから生まれる優しい独特な味わいが好きなんです!」

↑《「断崖の吊り橋」大杉谷》部分

↑《「断崖の吊り橋」大杉谷》部分
水彩画ならではの、柔らかな絵の具のにじみと偶発的な色の交わりに注目してみると、より一層作品を楽しめそうです。
ヒミツ②「作品を描く前に「〇〇」を決めておく」
2つ目のヒミツは、R.takiさんが作品を描く前に決めている“〇〇”に迫ります。
その“〇〇”とは、“額縁”。実はR.takiさん、絵を描き始める前から、どんな額縁で絵を額装するのか、既に決めているのだそう。
みなさんは“額縁”について考えたことがありますか?
額縁は作品の一部。絵の魅力をより高めてくれる大切な役割を担う存在です。どんな額縁を選ぶかによって作品のイメージが大きく変化するといっても過言ではありません。
では、絵を描き始める前に額縁を決めるR.takiさんは、どんな想いで額縁を決めるのでしょうか。
たとえば、《「断崖の吊り橋」大杉谷》の場合。彼が実際にトレッキングする中で感じた「高所ならではの恐怖」や「断崖絶壁の迫力」をより表現するために、黒色の額縁を使用しているそう。
黒といえばどこかかたいイメージになりすぎそうですが、絵と額縁の間に“マット”を挟むことで、柔らかい印象に仕上げているのもR.takiさんならではのこだわりポイントです。

↑《「断崖の吊り橋」大杉谷》部分
額縁を決めることから始まり、絵の構成を考えていきます。
吊橋ならではの“張り詰めた緊張感”や“恐怖心”が表現されているこの作品。あえて高所と低所をはっきりと描かないことで、見る人の想像を掻き立てるように描いているのだそう。
是非あなたも、自分の想像を膨らませながらアートを楽しんでみてください。
《「運河と街のハーモニー」ブラーノ島》
サイズ H41.5cm × W53.0cm
友人に勧められ、R.takiさんが訪れたのは、イタリア・ブラーノ島。気がつけば、その“可愛らしいカラフルな街並み”に魅了されていたのだそう。
実は漁師町でもあるブラーノ島。漁師がひと目見て自分の家を判断できるようにと、カラフルな建物が多く並んでいるのだとか。
《「運河と街のハーモニー」ブラーノ島》は、R.takiさんがイタリア・ブラーノ島でみた“人々が暮らす中で生まれた美しい街並み”と“観光客”の調和を表現した作品となっています。
この作品には一体どんなヒミツが隠れているのか、見ていきましょう!

↑R.takiさんが実際に訪れたイタリア(写真提供:R.takiさん)
ヒミツ①「海外の風景ならではの色づかい」
R.takiさんの作品には、日本の風景と海外の風景を描いた作品の両方がありますが、それらを見比べると、全く違った印象を受けるから不思議です。一体どうして異なるテイストの作品に感じるのでしょうか?
そこには「色」に関するヒミツが隠されていました。
日本の風景画を描く際には、たくさんの色を使わず、トーンを抑えて描くのがR.takiさんのこだわり。また、あえて立体的に描かないことも意識されているのだとか。
反対に、《「運河と街のハーモニー」ブラーノ島》のような海外の風景画を描く際には、色の彩度を高め、“油絵風”な表現を意識して描いているのだそうです。

↑左:《「音の無い世界」大正池/上高地》, 右:《「運河と街のハーモニー」ブラーノ島》
また、それらの作品に使用する「色」にもR.takiさんならではのこだわりが。
「市販の絵の具そのものの色では描かず、自作した色を使用して描いています」

↑R.takiさんが普段使用している画材(写真提供:R.takiさん)
「青色の中にもたくさんの色がありますよね。そう考えると色って無限にあると思うんです。より自身の描きたいものを忠実に表現するためにも、いろいろな色を組み合わせて表現することは、制作をする上で大事にしていることの1つです」
ヒミツ②「海外らしい額縁のセレクト」
2つ目のヒミツは「額縁」。
絵を描く前に額縁を選ぶR.takiさんですが、日本の風景画には“シックな色の額縁、海外の風景画には“華やかな色合い”や“アンティーク調”の額縁を使用するのがこだわりだそう。

↑《「運河と街のハーモニー」ブラーノ島》部分
《「運河と街のハーモニー」ブラーノ島》は、海外の風景を描いているので、アンティークな雰囲気を感じる黒色の額縁をセレクト。
華やかな色合いを引き立ててくれる黒色と、どこかヨーロッパのアンティークな雰囲気を感じる額縁が、作品の魅力をより高めてくれています。作品に描かれた風景はもちろん、色合いや額縁などアーティストならではの細やかなこだわりを感じながら、作品を鑑賞してみてはいかがでしょうか?
最後に
今回は「“冒険の感動”を描く、絶景アート」をテーマに、R.takiさんの作品を紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?
水彩で風景画を描くR.takiさん。実際に自ら足を運んで体験したからこそ描けるリアルな臨場感や風情の美しい色合いを是非、味わってみてください。